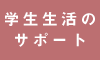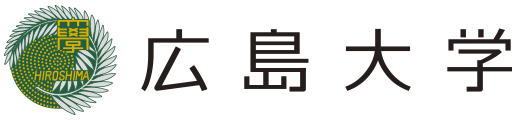3.意見交換会の内容について
【学生の主な意見】
「飲酒運転について(原付等を含む)」
発表資料「飲酒運転について(原付等を含む)」pptx
① 広大の対策について,及び学生の認識
・飲酒運転などが発生した際,学生全員にメールで注意喚起をしている。
・交通安全講習会の実施
→自転車利用者など,受けていない学生がいると感じる。
・学内や学外(居酒屋など)に飲酒運転撲滅のポスターの貼付を依頼している。
→あまり見たことがない。
② 飲酒運転についての学生の意識
・お酒を飲んでも自転車には乗る人が多い。
・自分だけの事故で終わることが多い。
・自転車での飲酒運転に対する意識が低い。
③ なぜ飲酒運転が起こってしまうのか
・飲み会に参加するとき,行きは自転車で行き,帰りは歩いて帰ればいいと思っていても,お酒を飲むことで冷静さを失い,帰りも自転車に乗ってしまう。
・友達が乗って帰ったら自分も一緒に乗って帰ってしまう。
・車やバイク等と違い,免許取得時の講習等がない。
④ 学生が考えた対策や提案
・未成年である一年次の時にしか飲酒運転についてのガイダンスがないので,身近に感じない。より身近に感じて受けることができるよう,成人になる三年次にもガイダンスを必修化する。
・ガイダンスに事故被害者を呼んで講演していただく,事故のVTRを見せる。
・罰則を示す。
・ガイダンス後にアンケートをとる。アンケートをとることで次年度への改善点を見つけることができ,かつアンケートを書くことで,再度ガイダンスの内容を意識するようになる。
以上,学生に印象づける対策が必要である。
「未成年者飲酒,飲酒強要について」
① 広大の対策について,及び学生の認識
・長期休暇前のメール送信や,もみじでの注意喚起。
→この2つ以外の対策は,学生間ではあまり知られていない。
② 未成年者飲酒,飲酒強要についての学生の意識
・法律で決められているから,いけない。
・新歓の場で先輩から飲酒をすすめられたら断れないかもしれないし,周りも場の空気を考えて止められないかもしれない。
・大学生の意識自体下がってきているが,強要することは減ってきていると感じる。
・調子に乗って飲みすぎた学生への対応・処置の仕方の指導がない。
③ 学生が考えた対策や提案
・未成年者飲酒による,実際のリスクと影響(健康状態,法的罰則など)をのぼりや掲示で示す。
・団体の中の成年の人が,未成年者がお酒を飲める環境に連れて行かない。たとえば,新歓を未成年者を含めて行うのであれば,居酒屋で行わないetc。
「占有離脱物横領,窃盗について(自転車盗難,万引きなど)」
発表資料「占有離脱物横領,窃盗について(自転車盗難,万引きなど)」.pptx
① 広大の対策について
・もみじ・広大メールによる注意喚起。
・駐輪場に二重ロック注意喚起ののぼり旗。
・放置自転車の処分。
② 占有離脱物横領,窃盗についての学生の意識,印象
・ビニール傘などだと自分のものと判別できなくて,間違えて持って帰ってしまう場合がある。
・悪意があってしている場合じゃない時もある(ボロボロの自転車が放置されていたので自分で修理して使った,など)。
・横領する方も悪いけど,取られる方も悪い(管理できてない)。
・罪の意識が低い。占有離脱物横領は万引き(窃盗)より罪の意識が低い。
③ 学生が考えた対策
・自転車の無料処分により放置自転車をなくし加害者となる可能性を減らす。
・傘立てをなくし,代わりに傘を入れるビニール袋を配布して持ち歩く方式にする。
・傘立ての前に注意喚起する。
・自分の目印になるものをつける。
・壊れた自転車を西2の自転車修理場所にもっていく。
「自転車のマナーについて」
≪霞キャンパス≫
① 広大の対策について,及び学生の認識
・広大が対策をとっていることは認知していなかった。
霞キャンパスでは特に対策を行っていないように感じたので,霞キャンパスでも対策を行ってほしい。
② 自転車マナーに対する意識
・意識は低い。
特に,自転車は軽車両であるという意識が低い。
・法律が変わったことは知っていた。
③ 自転車マナー,駐輪マナーの悪い例とその原因・影響
・駐輪スペース以外に駐輪してしまう。
自分の学科の講義室に近いところに停めたいが,近くに駐輪スペースがないため,無理やり止めている。
→歩道にはみ出したり,通行の邪魔になっている。
・並走。
友達と話していると自然にそうなってしまう。
「周りに邪魔にならないならいいかな」という考えが先行してしまう。
→通行の邪魔になる,正面衝突する可能性がある。
・傘差し運転。
カッパは左右の視界が悪い。保管に困る。
→片手運転になり,事故を起こす危険性が高まる。
・飲酒運転。
居酒屋などで,車を運転する人への酒類の提供は断られるが,自転車に乗る人には特にない。
→法律違反,事故を起こす危険性が極めて高い。
④ 学生が考えた対策
・駐輪スペースを増やす。
・雨の時用に屋根を設置する等,設備を整備する。
・自転車専用レーンを整備する。
・雨の日は徒歩で移動する。
・お酒を飲んだら自転車にも乗らないという意識を高める。
≪東千田キャンパス≫
① 広大の対策について
・飲酒運転や無灯火走行について,もみじでの掲示や広大メールでの注意喚起。
・カラーコーンの設置により駐輪スペースの明確化。
② 自転車のマナーについて現状と学生の意識
・並走。
・放置自転車が多く,邪魔。
・安易な飲酒運転(意識が低い)。
・スマホを使用しながらの運転。
・法改正の効果はいかほどか。具体的内容まで周知されていないのではないか。
・自転車の多様化(ロードバイク,ピスト,ママチャリ,ミニチャリ)。
・事故などの結果予測をしていない人が多い(怪我の程度,損害賠償など)。
・自転車が車両であるという意識の欠如。
・自転車保険の未浸透。
③ 学生が考えた対策
・歩道を運転してよいかどうかが場所により違い,わかりづらいため,統一する。
・自転車保険に入る。
・夜間時・走行時はテールライトをつける。
・自転車を有料登録化する。
・入学時のガイダンスでの説明等で,走行時の左側通行,車道を走る際の注意等明確な知識をつけさせる。
≪東広島キャンパス≫
① 広大が行っている対策,及び学生の認識
・交通安全講習会の実施を検討。
→あまり知られていない・効果がないように感じる。
・大学の職員がマナー指導。
→あまり知られていない・効果がないように感じる。
・駐輪区域外に停めている自転車のロック。
→全てをロックせず,無作為にロックされているため,学生は「今回はロックされなかった」程度の意識しかしておらず,あまり効果がないように感じる。
・歩行者と自転車の分離(道の色分け)。
→空いている方を進んでしまうので,効果が薄いように感じる。
② 現状について
・譲り合いがない。
・信号無視。
・並走。
・無灯火。
・傘差し運転。
・イヤホンをつけたまま走行。
③ 学生の意識について
・そもそも悪いことをしている自覚がない。
・自転車を毎日乗るから常に気を張っていられない。
・よく乗るから違反をしてしまう。
・集団でいるから責任感が薄くなって,少しくらい違反してもいいかと思ってしまう。
・授業に間に合わない等の理由で時間に余裕がないため,信号無視をしてしまう。
・傘差し運転は交番の前等だけ避け,ばれなければセーフという意識。
・西条に学生しかいないから馴れ合いになっていて,違反した者について甘い。
・自動車と衝突しても責任はどうせ自動車が負う。
④ 有効な対策について
・交通安全講習会への参加を徹底させる。
・違反自転車をすべてロックするまたは没収などの罰。
・交通安全を意識させる設備をきちんとしたものにする。
(ラミネート加工の薄いものではすぐ破損するため)
・規範意識会議に参加させる人数を増やす。
・自己責任になることを自覚させる。
「試験でのカンニングについて」
① 広大の対策について,及び学生の認識
・カンニングによる不正の場合の処分内容をもみじに掲示。
・学生証を机の前に置かせて顔確認。
・テスト用紙にも処分内容を記載。
・携帯をしまわせる。
→効果はあるのか疑問に感じている。
② カンニングについての学生の意識・イメージ
・よくないことである。
・魔が差してしまう。
・普段勉強していないからしてしまう。
・スマートフォンでカンニングしやすくなっている。
③ なぜカンニングが起きるのか
・単位を取るため。
・"短期間"で"大量"の勉強に追いつめられるため。
④ カンニングによる他者への影響
・不公平。
・自分は頑張って勉強しているのに,気分が悪い。
⑤ 学生が考えた対策
・学生同士の注意は難しいため,見回りの教員を増やす。
・スマホの徹底管理。
・筆箱をしまう。
「公共施設利用上のマナーについて」
① 現状について
・自転車,原付の放置(そのまま卒業することも)。
・(特に夕方以降の)教室利用の仕方が汚い,食べ物のゴミが残っているなど。
・守れて当たり前のマナーを守れていない。
だから様々な注意喚起の張り紙がある。
② なぜマナーを守らないのか,学生の意識
・誰も見ていないだろう,めんどう,などといった甘え。
・遅刻しそう,次の授業に遅れる,などの時間的余裕のなさ。
・自分くらい構わないだろうなどという,自分中心の考えや潜在的な意識。
③ 学生が考えた対策
・マナーを教える(例:文学部がおこなっているマナー講座など)。
・掲示をもっとユニークなものや目につきやすいものに変えてみる。
・教えるだけでなく,ひとりひとりにマナーを守ることについて意識してもらう。
・オリキャンや教養ゼミなどにもマナーについてのプログラムを組み込む。
【質疑応答及び意見交換】
・広島大学としての取組を知っている学生が少なかった。
・今日の話し合いの中で知ったことを周囲に知らせてほしい。
・占有離脱物横領やマナー違反など,してはいけないことはみんな知っていると思う。それをすることによってどういうことになるのかの意識・考えが足りていないのではないかと思う。大学として,広報することも大事だが,教養ゼミ等で,それをすることによってどうなるか「みんなで考えてみる」ことが重要なのではないかと感じた。
・学生の認識と職員がやることの認識にギャップがあるのではないか。もっと学生と話し合う機会(広い場)が必要かなと感じた。
・参加した学生は規範意識が高い学生だと思う。参加していない学生にどう規範意識を持ってもらうかが重要だと思う。